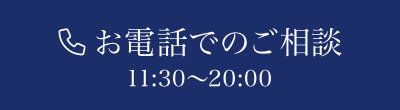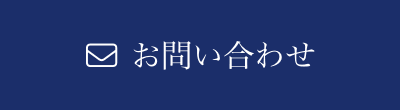飲食店などでは、お店の入り口に暖簾がかけてあると営業中、暖簾がしまってあると準備中を意味する「暖簾(のれん)」。営業時間を知らせるだけでなく、お店の「顔」として看板の役割を持つ暖簾には、他にもさまざまな役割があります。
このコラムでは、暖簾の意味や由来とあわせて、代表的な用途・役割についてまとめていきます。さらに、暖簾の“色”による意味の違いについてもご紹介しますので、日本の伝統製品の一つ、「暖簾」について深く知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
暖簾の意味とは?いつから使われているの?
漢字に「簾(すだれ)」という字があることからもわかる通り、「暖簾(のれん)」とは、お店の入り口や室内などに吊り下げる布製の簾(すだれ)のことを意味しています。
この暖簾ですが、もともとは「のんれん」と読まれていたそうです。それが、長い年月を経るごとに「のんれん」から「のうれん」へと変化し、今では「のれん」という名称で呼ばれています。
この暖簾の起源については諸説あるようですが、平安時代ごろには既に使われていたと言われています。当時は、日除けや風除け・目隠しなどを目的として、建物の軒先に布をかけていたのですが、鎌倉~室町時代ごろには、家紋やお店の名前などを入れて、看板や宣伝として使うようになっていったそうです。
今では、日除けや風除けとしてだけでなく、さまざまな用途で私たちの生活に溶け込んでいる暖簾。長い歴史と伝統を持つアイテムの一つですが、これからも私たちの暮らしにあわせたスタイルに進化していくかもしれませんね。
【暖簾をかける意味】用途・役割とは?

もともとは日除けや風除けなどの用途で使い始めた暖簾ですが、現在においてはどのような用途・役割があるのでしょうか?
看板
お店の名前やロゴを入れた暖簾には、看板や目印としての役割があります。寿司屋や居酒屋などの飲食店を中心に、呉服屋や銭湯など、さまざまな業種で使われているので、皆さんも目にすることが多いのではないでしょうか?
一般的には、お店の入り口に暖簾がかけてあると営業中、暖簾を下ろしていると準備中という意味があり、暖簾の有無によって営業中かどうかを判断する目印にすることができます。
日除け・風除け・ほこり除け
看板としての役割以外で、代表的な暖簾の用途と言えば、やはり日除けや風除け、ほこり除けなどではないでしょうか?
例えば、直射日光が当たって商品が傷んでしまう、風で商品が動いたり飛んでいってしまったりする、人通りが多くて砂ぼこりが舞ってしまう…などの場合に、暖簾を利用することでそれらを軽減することができます。
目隠し
暖簾を見られたくない場所にかけることで、目隠しにもなります。
例えば、飲食店なら厨房やお手洗いの入り口に掛けておくことで、店内にお客様がいても視線を遮ることができますし、お店の入り口にかけておけば、ドアを開けたままにしていても、通行人からは店内が見えないように隠すこともできます。
仕切り
暖簾を上手く活用することで、店内や部屋などの空間を圧迫感なく仕切ることもできます。
飲食店なら前述の厨房やお手洗いの入り口はもちろん、個室の間仕切りとしても活躍しますし、ご家庭なら生活スペースとワークスペースを分けたいという時にも、暖簾を活用することで簡単に仕切ることができます。
装飾
仕切りや目隠しとしての役割のほかに、インテリア・装飾としての役割もあります。
特に、暖簾にはさまざまな素材の生地が使われるため、デザインだけでなく色味や手触りなども多種多様。イメージにあわせた暖簾をインテリアとして活用することで、居心地の良い空間を演出することができるほか、店舗ならブランディングにも役立ちます。
色にも意味がある?暖簾の色使いについて

さまざまな役割を持つ暖簾。今では、さまざまな色やデザインで製作されていますが、昔は業種によって暖簾の色が分かれていたのをご存じでしょうか?
ここからは、暖簾の色による違いや意味についてご紹介していきます。
紺・藍色の暖簾の意味
紺や藍色の暖簾は、信頼や手堅さを重視する商家で多く使われていました。
紺や藍色に染める際は「藍染め」で染めるのですが、この藍染めの染料となる植物の“藍(あい)”には、紫外線防止効果や防虫効果などがあります。そのため、特に虫が天敵となる呉服屋や酒造業、蕎麦屋などでは、藍染の暖簾が持つ虫除けの特性が重宝されていたようです。
白の暖簾の意味
薬屋や菓子屋で使用されていたのが、白の暖簾。実はこの「白」は、菓子屋でよく使われる「砂糖」の色が白かったことに由来するそうです。
さらに、日本では昔、砂糖を薬として使用していたこともあり、薬屋でも白色の暖簾を使っていたそう。今では白色が持つ清潔でさわやかなイメージから、夏の暖簾を白にしているお店もあります。
赤の暖簾の意味
例えば、今でもラーメン屋や居酒屋などの飲食店で多く見かけることがあるかもしれませんが、その昔、店の入り口に赤い暖簾をかけていた安い飲食店が多かったことから、赤い暖簾には「安価な飲食店」という意味があります。
さらに、赤は食欲を増進する色ともいわれており、暖簾の色を赤にすることで視覚的にも心理的にもお客さんの興味を引く工夫をしていたようです。
ただし、赤い暖簾はあっても、赤文字の暖簾はあまり使われていません。その理由は、「赤い文字=赤字」を意味するから。あくまでも赤が使われるのは、暖簾のベースの色となります。
茶色の暖簾の意味
茶色の暖簾は、お茶屋や煙草屋などで使われていました。
この茶色も商品の色のイメージからくるもので、江戸時代ごろによく飲まれていた番茶の色や、煙草の葉の色が茶色だったことから、茶色の暖簾が使われていたと言われています。
柿色の暖簾の意味
柿色の暖簾…というとイメージしにくいかもしれませんが、「かちん染め」という染色技術を使った際に出る赤みがかった茶色のことを「柿色」と呼び、その色を暖簾にも使っていました。
この柿色の暖簾を使っていたのは、吉原や島原といった花街の店や、その遊女たちを呼ぶことのできる高級料亭や宴会場などの限られた場所だけだったと言われています。
その文化も年月とともに廃れていき、現在では、その色のイメージからお茶屋や菓子屋などで使われることもあります。
紫の暖簾の意味
神秘的で位の高さを意味する紫色は、古くから貴族や皇族などの高貴な人物だけが身に付けることが許されていた色。庶民にとっては「禁色」とされていたため、暖簾でも使われることはありませんでした。
しかし、江戸時代に入ってから、金融機関から借金をしている場合には紫色の暖簾をかけなければいけないというルールができ、借金の目印として使われるようになったそうです。
現代では、紫の暖簾に借金をしているという意味はなくなり、気品や厳かな雰囲気を持つ色として暖簾にも採用されています。
暖簾の意味や役割を知ってこだわりの一枚を
今回は、暖簾をかける意味やそれぞれの色の暖簾が持つ意味についてご紹介してきました。
日本で古くからさまざまな用途・役割で愛されてきた暖簾。特に店舗では、お店の顔ともいえる重要な役割を担っているため、こだわりの一枚を求めている方も少なくありません。
暖簾は、生地や染料・染色方法などによって、さまざまな表情を見せる魅力的なアイテムです。店舗や自宅などにかける際には、ぜひ、こだわりの一枚をオーダーしてみてはいかがでしょうか?
染物を通じてお客様の大切な「こだわり」をカタチに

水野染工場「日比谷OKUROJI店」は、北海道旭川で明治40年から染物屋を営む株式会社水野染工場が「より染物を身近に感じていただけますように」との願いを込めて東京で展開する染物専門店です。
手ぬぐいや藍染商品の販売以外にも、藍染のデモンストレーションや体験イベントを行うなど、藍染を通じてお客さまの「想い」に寄り添う商品をお届けしています。
半纏・法被、暖簾、旗、手ぬぐい、帆前掛け、神社幟、神社幕…など、印染製品のオーダーメイドについても、直接店舗でご相談いただけますので、ぜひ一度、水野染工場「日比谷OKUROJI店」にお越しください。